法廷技術ワークショップに参加して
大橋 賢也 (弁護士)
平成24年7月27日、28日の両日にわたって、横浜弁護士会館において、法廷技術ワークショップが開催されました。これは、法廷での尋問や弁論の技術を学ぶもので、日弁連裁判員本部法廷技術プロジェクトチームから講師の先生方が来てくださいました。事前に、殺人未遂事件の起訴状や供述調書等の証拠を渡され、冒頭陳述(裁判が始まった直後に行われるもので、これから証拠によって証明しようとする事実の陳述のことです)、検察側からの主尋問・反対尋問、弁護側からの主尋問・反対尋問、そして最終弁論を用意するように、という課題が出されました。私ばかりでなく、多くの弁護士が、尋問や弁論を行うときは、紙に打ち出したものを参考に、若しくは読み上げて行うものなのですが、ワークショップでは、冒頭陳述、尋問、弁論すべてにおいて、何も見てはいけないという制約の下に行われました。
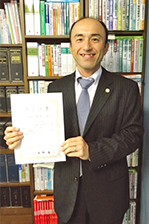
なぜ、何も見ずに(ペーパレスで)弁論等を行うべきなのかにつき、上記プロジェクトチーム座長の高野隆先生は、「人を説得したり人と共感するというのは、その場において作り上げられた言葉でないと無理だ」。と仰っています。言うは易く行うは難しで、特に弁論をペーパレスで行うことは、非常に難しいものです。ただ、ワークショップで高野先生が実演されると、冒頭陳述であっても弁論であっても、すごく引き込まれるものがあり、説得力が全く違うものだと感じました。また、ワークショップでは、主尋問の目的は何か?反対尋問の目的は何か?それぞれで聞くべきことは何か?やってはいけないことは何か?etcについて、徹底的に指導していただきました。これらは、知識としては知っていても、いざ実践してみると本当に難しく、しかもペーパレスで行ったため、途中で止まってしまい、次に何を聞いたらよいのか分からなくなってしまうなど、普段は経験しないことも経験させていただきました。ワークショップでは、自分が実演しているところを録画していただき、実演後すぐに確認し、問題点等を指摘していただいたため、自分の癖や改善点も分かり、非常に勉強になりました。今回のワークショップは、刑事事件を題材に、尋問や弁論のやり方について学ばせていただいたのですが、今回学んだことは、民事事件での尋問にも必ず役立つと思います。今回のワークショップで得たものを日々実践し、より高度の法定技術を身に付けていきたいと考えています。

